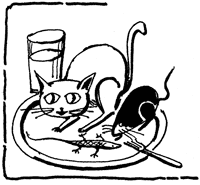グラマン・カーチス戦闘機十数機が一日3〜4回は定期的にやって来る。いざ米機の空襲となると、兵はまずわれさきにタコツボに飛び込む。機銃掃射は一様に45度の角度なので、タコツボの中には命中しないのである。
しかし日本兵がいるとわかれば、今度は一屯爆弾数個が所かまわず投下される。これは大きな破片が真っ赤に焼けて、小山の濠も吹っ飛ばす威力である。戦争という二文字は、人間の尊い運命を一瞬にして「生か死か」に決する。
この爆弾が投下されれば、爆風とともに何十人もの将兵たちの身体は散乱状態となってその形も残らない。それは電光石火とも言うべきもので、異様で強烈な閃光の中、自分は幼少時代に見た落雷を思い出したが、もちろんそれ以上のものであった。このときのモロン地区部隊の状況は、いかにしても筆舌に語ることはできない。
もう自分たちは部隊の命令で行動するのではなくなった。まず糧秣の補給がまったくない。自分が食べる食物は、どこからか求めなければ、飢え死になってしまう。初年兵2〜3人が山の峰づたいや、谷底まで駆けずり回って何でも食べる物があればと捜し求める。ヘビ・トカゲ・ネズミ・バッタ・コオロギなど大好物であった。時には雨蛙を煮炊きすることができずそのまま足から皮を剥いで刺身として戦友たちと食べた。塩味を付けて食べると美味しかった。
いつの日か忘れたが、どの班長殿であったか、
「今晩はかしわ料理だ、みんなご馳走だから」
と言われたので、5〜6名の兵隊たちは大いに喜び合った。
なるほど、鍋に野草と白い肉のような物が小さく刻み込まれていた。かしわのすき焼き、砂糖もなければ醤油もない。2〜3個食べてみると、白い肉は柔らかく、何の味気もなかった。4〜5名が食べ終わると班長殿は、